情報発信記事の選択は、部員の勝手な判断で?!
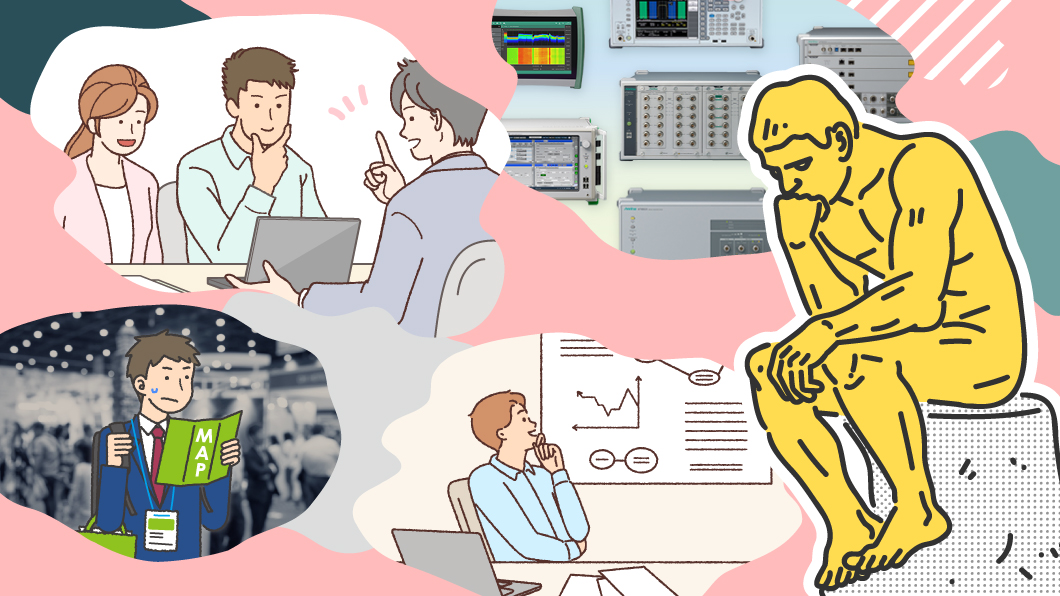
私の所属する部署では、情報発信ツールとしてWebサイト(本コラムのほか、アンリツの製品紹介やニュースリリースなど)に加え、メールマガジン、SNS(Facebook)などを使用しています。
その使用目的について、販売促進ということは否定できませんが、そのほかに、たまにはホッとする話題の提供も織り交ぜるなどして、皆さまの記憶の中にアンリツがいてもらえると良いなあ、などと単純に思っていたりします。
デジタルマーケティングで必要なことは営業と同じ?!
情報発信ツールの性格
Webサイトの製品ページはその性格上、製品情報の提供に特化しており、それ以外の情報提供はありません。新製品が出れば、取捨選択をせずにどんどん載せていく性質のものです。ニュースリリースのページも、扱う情報の種類は増えますが、似たようなものです。
一方で、本コラムやメールマガジン、Facebookは性質が違っていて、地球上の皆さまとのコミュニケーションツールとしての位置づけが出てきます。皆さまが関心を持ちそうな記事や話題を選ぶという考えが出てきて、提供情報の幅も広がります。ということで、極端に言えば部署のメンバーの好き勝手にできるとも言えますが、やはりその点は常識をわきまえつつ自制を心がけております。
提供情報の選択と課題
ところで、これらのコミュニケーションツールで提供する情報について、掲載スペースや提供機会が限定されることがよくあります。たとえば、複数の新製品の中から一つを選択しないといけないときにはどうでしょうか。少し悩んでしまいます。このとき、ロダン作のブロンズ像「考える人」のように、固まった状態のままになるわけにはいきませんよね…。
選択の基準と選択への備え
先ほども書いた通り、部署のメンバーが好き勝手に選べますので、提供情報をくじ引きで決めても良いのです(笑)。しかし、発信するからには何らかの効果を得たいものです。
そこで第一に思うのが、皆さまの記憶の中にアンリツがいてもらえると良いなあ、ということです。アンリツのお堅い製品でいかに記憶に残してもらえるか、はなはだ難問ではあるのですが、選択順位が高くなるのは、記憶してもらえる読者が一番多い製品や世の中で話題になりそうな製品、といった感じです。でも、製品がそれらに当てはまるか、どうやって知りましょうか?
ここで重要なのが、対象製品の市場の様子を想像できること。私は、対象製品自体のほか、想定されるお客さまやマーケットの大きさを社内外のレポートを読んで知り、実際に営業部のメンバーから製品の反響を聞くこともあります。展示会で、説明員にお客さまの反応を聞くこともあります。こうした市場理解の結果をベースにすると、コミュニケーションツールによる提供情報の選択順位は、自信を持って決められます。
結局、コミュニケーションツールの有効活用には、営業部やマーケティング部のメンバーと同じように、製品や市場に関する理解が必要と感じます。
デジタルマーケティング施策では、ツールを使えるだけではバランスが良くないということですネ。
おまけ情報です。アンリツからの情報発信をお楽しみください。
